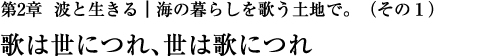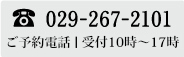海を歌う家
生まれ育った家は、もっと海の近く。海が目の前だったの。
嵐の前には、家の前で、舟主が舟を並べて縛っていて、それが当たり前の風景だった。
家の中にいても海を感じる家。
もちろん、波の音もずっと聞こえてるわよ。
そこで歌って練習してた。(浜久美子さん・談)
ことわざが言うように、歌は世の中の現実のありのままを映し出し、世相もまた、歌とともに移り変わってゆくものでしょう。各地で、長い年月を変わらぬ歌詞で歌い継がれてきた土地の歌、民謡の世界から見る「歌と世」の関係はどうでしょうか。何が移り変わり、何が変わらぬものとして在り続けているのでしょうか。 大洗には古くから歌い継がれている民謡「磯節」があり、いまでは国内でも広く知られ、日本三大民謡の1つと称されています。民謡は、民衆の歌謡。民衆の生活の中で生まれ、共感性をもって口伝えで広まり、その多くが作者不詳とされています。江戸時代に、漁民の暮らしや櫓漕ぎ唄から生まれたと言われる磯節もまた然り。明治期になり補作されたものなども多く、いまでは100を超える歌詞があると聞きます。『大洗町史』に書かれている、明治期にもよく歌われていたという出漁などの情景が目に浮かぶ歌詞から三首を紹介します。
「沖で鰹のせのたつ時は、四寸あつみの櫓がしなる」
「沖に見ゆるは大亀磯よ 鴎も舞いくる真帆片帆」
「三十五反の帆をまきあげて 行くよ仙台石巻」
前回の記事でもお話を伺った、蓼沼香未由(たてぬまかみゆ:大洗町生涯学習課文化振興係)さんによると、大洗がある旧磯濱村の江戸時代の漁業は、イワシ漁とカツオ漁と、それらの加工業が中心だったということです。イワシをそのまま乾燥させた干鰯(ほしか)は、タバコ畑の肥料として重宝されて那珂川の河口から帆掛船に積まれ遡上して、中流域の畑へと運ばれていきました。大洗の海に注ぐ那珂川の中流域では、江戸の元禄年間の頃には、葉タバコの栽培が隆盛を極めていたといいます。そして中流域のタバコ農家は、農閑期になると川を下って大洗にやってきます。目的は、潮湯治です。

保養地・大洗の始まり
潮湯治とは、いまでは聞きなれない言葉ですが、皮膚病などの治療に、海水を温めて浸かったり、海水に直接浸かったりすること。江戸時代初期には、海水温浴が皮膚病治療に効果が有ることを紹介した中国の書物が日本に伝わり、後期には、直接、海で海水に浸かる海水冷浴も普及していたそうです。炎天下に収穫などの作業が続くタバコ農家は相当な重労働であり、タバコの成分で皮膚が荒れることも多かったのではと推察できます。 明治時代に入ってからも潮湯治にくる人は絶えず、内陸の農民だけではなく東京からも近場の浴場として大洗に人が集まるようになりました。大きな変化は、明治20年代。長期滞在者のための旅館が増え、本格的な海水浴場が開設されました。江戸末期(1865年)に料理店として大洗の海岸沿いに開店した「魚来庵(ぎょらいあん)」は、明治3(1870年)年から、旅館としても営業を始め、潮湯治の海水浴客が増えてからは増築や別館の建設を続けています。 里海邸の前身である「金波楼(きんぱろう)」も、残された記録からわかるのは、明治21(1888)年には、大洗の4軒の海水浴旅館の1つとして現在の位置で多くの潮湯治客を受け入れ始めていたということです。初代は、天保11(1841)年生まれの石井藤介。大正15年に刊行された『東茨城郡誌』の「第10編・人物」によると、明治初期から漁業を始め、カムチャッカ視察ののち、料理旅館としての金波楼の傍ら、明治25(1892)年には鯛味噌を開発したとの記述もあり、のちに蒸気船を購入したり、塩の売買を行うなど、多角的な視点と行動で明治期の大洗の発展に寄与していたと思われます。
明治26年には海水浴旅館は6軒に増え、短期間に大洗を訪れる人が増加したことが伺えます。そこには、明治22(1889)年に、栃木県の小山と水戸との間に水戸鉄道が開業し、那珂川で運行する蒸気船との接続で、大洗への人の流れに拍車がかかったという背景もあります。
明治20年代は、太平洋に面した常陸の国の一漁村・大洗が、前章で紹介した「信仰の土地」であることに加え、全国的にも有名な保養地としての役割も始めた時期でありました。ほどなくして、潮湯治という医療目的の海水浴から、レジャーとしての海水浴へと役割も変わり、場所についても、大正・昭和期には、大洗から南方の磯浜の築港内へと
移り、昭和後期の大洗港建設によって、さらに南の埋め立て地、大貫地区の大洗サンビーチへと変遷がみられます。

漁民の唄として、座敷唄として
明治時代中期は、磯節の世界においても大きな転換期となりました。舟の上で、磯で、浜辺で、歌い継がれてきた節に「はやしことば」や「伴奏」が付き、歌詞も増え、お座敷で歌われるようになりました。 江戸時代から水戸藩唯一の歓楽街として栄えた大洗の祝町で引手茶屋を営む渡辺精作が、その立役者でした。『大洗町史』によると、渡辺は漢詩や和歌もたしなむ文芸人で、明治中期には竹楽房の号を名乗り磯節の研究を始め、歌詞やはやしことばを加えながら芸妓たちに教え始めたそうです。それ以降、芸妓たちによって、明治30年代前半には、東京、関西、東北の花柳界に広められ、踊りも生まれ、全国的に有名なお座敷唄として育ってゆくことになります。
里海邸の前身、金波楼では、宿泊客の座敷に招かれた芸妓たちが、洗練された磯節を披露する一方で、ある時、ある一室で、無名の漁民の中から生まれた際の原初的な情景、そこに立ち返るような磯節をめぐる出会いが生まれていました。その磯節の歌い手を見出したのは、場所が終わって金波楼で休息をとっていた、水戸出身の力士、常陸山(第19代横綱)でした。常陸山は宿に、按摩(あんま)を頼み、マッサージを終えた男性にも酒を勧め、会話を交わしながら何かの余興をと、所望します。それに答えて男性が歌ったのが、舟の上で父親から口伝えで習い、歌い続けてきた磯節でした。
男性の名は、関根安中(せきねあんちゅう、本名・丑太郎)。明治10年に大洗で生まれ、漁師の父親と10歳くらいから舟に乗るも、次第に視力が弱まり漁を続けることができず、半盲の按摩師として働き始め、四年が経った頃でした。『大洗町史』には、こう書かれています。
「常陸山は、海の男の哀歓を誘う安中の美声と自由奔放な歌声に深く感動し、その後、常陸山は、地方巡業の旅先へ安中を同行して、『わしの郷里の安中というもので、郷里の歌磯ぶしの名人です』と、後援会が催してくれる宴席その他で、安中を紹介し、安中は得意の『磯ぶし』を歌って、全国を回った。」
常陸山と安中の出会いは、明治10(1877)年生まれの安中が24歳の頃という記録があることから、明治35年頃のことなのでしょう。それから大相撲の巡業とともに「磯節」も全国を回り、大正11(1922)年にはレコードも発売されています。

磯節発祥の地碑。松林の中で素朴な安中の歌が流れる
「安中さんは、金波楼さんで一仕事終えると、自宅に帰る途中で、必ず、うちに立ち寄っていたみたいです」
と、教えてくれたのは、大洗の明神町で表具屋を営みながら尺八を中心に民謡の活動を続けている、宮内保明さん。宮内さんは、安中の従兄弟の子にあたるといいます。
「一の鳥居が、コンクリートじゃなくて、まだ木の鳥居だった頃だね、あの辺まで安中さんが歩いてくると、歌でも口ずさんでいたんですかね、私の親父が、それが聞こえていたのか、『そろそろ安中が来るから、お茶を入れろ』と言っていたのを覚えていますよ」
明治の頃、舟の上で、口伝えによって父から教わった安中の磯節。時代は変わり、昭和に入り、父の勧めで民謡の世界に入った宮内さん。歌は世につれ、世は歌につれ。昭和の時代の磯節にまつわる風景を伺っていきましょう。