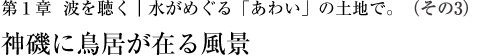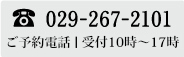めぐる水
『大洗町史』には、「江戸時代文政年間の『常陸紀行』(黒崎貞享著)は、大洗磯前神社が本邦医家の始祖であるとしている。とくに、眼病によいといわれ、磯浜にいる目の見えない人は他村出身者だけだと言われていた(水戸藩神社録付属)。天保の頃には、大洗みたらしの霊水がとくに効くといわれ、多国からも眼病治療のために多くのものが訪れ、茶屋が繁盛したという(『磯浜誌』)」という記述もあります。漁師さんたちだけでなく、さまざまな人が神社には助けられていたことが伺えます。
「そうですね。漁師さんたちだけでなく、昔から、地域の人は大洗さんには助けられていると言ってくださいますね。ここは昔から那珂川や涸沼川(ひぬまがわ)からの水や山に降った雨水が地下水となって神社の敷地を通り、階段の下で湧き水となって流れ出ていたんです。みんなその水を生活に使っていたし、目の病気にも効くと評判になっていたそうですよ」
なぜ、眼病に効くのでしょうか。
「霊水が効くと言って、目を洗いに来ていたんですね。目洗しと書いて、みたらしです。ここの水は腐りにくいと言われています。あるお医者さんが、ここの水を汲んで帰って、2ヶ月おいていても腐らなかったと聞いています。雑菌が少ないのでしょうか。殺菌力みたいなものがあるのかもしれませんね」
里海邸がある宮下地区の水道は、この地下水からひかれているそうで、里海邸の浴場の水やお風呂にも使われているそうです。「うちのメダカも神社の水でないとだめなんです。水道水だと弱ってしまいます。それから、波打ち際の石の間を流れる水は、なめてみると、あまり塩っぱくないんですよ」と里海邸のご主人が教えてくれました。
鎮守の杜の地下を旅してきた水が湧水となって海に流れ出ている情景も、過去のものではありません。大きな引き潮の時には、大洗海岸の波打ち際で目を凝らして耳をすませば、水が染み出し、トクトクと海へ流れていく様を見ることができます。



遠い昔から絶えることの無い水のめぐりは、地域の日常を潤し、
それでもなおあまりある地下水や、この土地に降った雨は、海へと還ります。
そしてまた、海の中や岩礁で、多種多様な生命を育みながら、
その一部は空に上り雲となって雨となって、また大洗の土地に還ってきます。
里と海が出会う土地。
日常と聖なる世界が出会う土地。
その「あわい」の境界を行き来しながら、
生命の繋がりの生態系を水がめぐります。
私たち人間の体の中も、隈なく水がめぐります。
荒磯で、波の音を聞きながら、大きな、小さな、水のめぐりをイメージします。
目と、耳と、感覚が開かれてゆき、
センス・オブ・ワンダーの世界に誘われる、「あわい」の土地です。
(お知らせ)
秋に公開予定の次章では、日本の三大民謡のひとつと言われる大洗発祥の「磯節」をキーワードに、漁師の町、保養地・海水浴場の町としての歴史物語を紐解きます。
簑田理香
栃木県益子町在住。編集者として、宇都宮大学地域連携教育研究センター所属・地域連携コーディネーター/特任准教授として、地域コミュニティ活動のメンバーとして、その土地の風土に根ざした健やかな地域づくりの事例研究や学びの活動、メディア制作などを行っている。益子の人と暮らしを伝える「ミチカケ」編集人。益子町「土祭」2012/2015プロジェクトマネージャー。地域編集室簑田理香事務所 主宰。

『海からの贈り物』アン・モロウ・リンドバーグ
吉田健一 訳(新潮社)/落合恵子 訳(学習研究社)
著者は、太平洋単独無着陸飛行に初めて成功した20世紀のアメリカ人飛行家、チャールズ・リンドバーグの夫人、アン・モロウ・リンドバーグ。第二次世界大戦後のアメリカ社会を背景に語られた、女性の暮らしや仕事、人間関係をめぐる思索の書です。物語は、ひとりで海の旅へ出た著者が滞在した島で実践する「モノの少ない簡素な暮らし」がもたらす心の効能を発見し、その魅力を詩情あふれる表現で語るところから始まります。そして、家族とともに過ごす日常の居住地であるコネティカットでの気の散るばかりの複雑な暮らしを振り返りながら、都会の日常生活がもたらす疲れの原因を突きとめてゆきます。心が疲れている…。現代人がそう感じる時に思い出して手に取りたい、一冊です